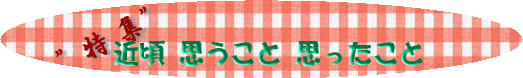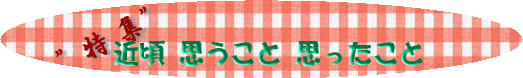|
今年我が家に受験生がいるので、スキーに行けないから思うのかもわかりませんが、暖冬だということです。タクシーのドライバーも言っていましたが、京都駅八条口を出発するスキー客を乗せたバスも、今年は少ないそうです。1月8日に丹後の与謝町に葬式に行ってきたのですが、7日から降っていた雪が心配されましたが、ほとんど雪の影響はありませんでした。20年〜30年前は雪深いところだったそうですが、ここ10年は雪があまり降らなくなったそうです。
地球温暖化の影響に違いはなく、このままのペースで行くとおよそ50年後には北極の氷が解けてなくなるとか・・・
地球規模の問題に、私のような者が出来ることは針の穴のように小さいことしか出来ません。でも50年後、私たちの子どもたちは生きているわけですから、何か出来ることからして行かないといけない、そう思います。買い物袋を持って買い物に行く。車を出来るだけ使わず、公共の乗り物を利用する。所謂、リデュース、リユース、リサイクル、リペアを実行していくことが、我々大人の緊急の責務だと思います。
ですが、自分の楽しみを大切にしたいのも事実です。いくら頑張っても、禁酒、禁煙、出来ません。子どもたちのために働いていると言うよりは、飲む為に働いているというのが正直なところです。これがないと、生きている楽しみがないのです。小さな事から、出来ることから、出来る範囲でやれることをやる。たいした人間でもない自分が子どもたちにしてやれることは、これじゃないかなと思います。
少し古いですが、「小さな事から、コツコツと。」これが、私が最近思うことです。
|