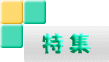経済について 20世紀の後半を経済一辺倒で走り続けた日本、その原動力は敗戦からの脱出と先進国の仲間入りであった。今私達が生きている時代は見方を変えれば、バブルと言う戦争に負けた敗戦国の状態ではないでしょうか、何かにとりつかれたように走り続けたバブル時代、まるで、帝国の異常な戦略によって植民地をふやし続け、幻の勝利に酔っていた時代のようではないだろうか、そうであるならば、まさに今は終戦後の日本であるに違いないでしょう。それと理解できれば私達がしなければならないこととして、子供たちや若者に伝えることは数知れず、先述のように彼らの無力感を生き生きとした物に替えるのは彼らの将来が魅力あるものであるかを形に表し示してあげ実際に目に見えるようにしてあげることが大切なことでしょう。 戦後を支え先進国の仲間入りを果たす要因は、国民のその意思が大きく反映していることは誰しもが承知のことです。労働者、猛烈サラリーマン、企業家、日本全体を称してエコノミックアニマルとまで言われた時代それはそう言われたくてやったことではないでしょう。しかし今一度そのハングリーな精神を経済優先ではなく、環境経済優先にすることで生まれてくるのではないでしょうか、これまでは、自分たちの生活が物質面で裕福な状態を求めて働き続けていたのですが、環境問題を大きくした私達は、その反対に環境先進国の仲間入りには程遠いものがあります。閉塞感のある経済を立て直すのではなく、新たな環境経済というものを構築していくことのほうが、私たち自身にも大きな夢が持てるような木がいたします。経済敗戦国日本その再生は、若者たちに対し彼らに未来があることを実感できる社会作りその基盤つくりが私達今を働く人々がやらなければならないことだと信じているしだいです。 この敗戦から脱出するには、環境先進国の仲間入りを目指すと同時に、経済ではトップを勝ち得たように、環境先進国としてのリーダーとなることなのです。 自然について 自然とは=あるがままの姿、流れあるその流れに添うこと、生き物として求められるままに求め合い、愛でるものの存在を互いに認知し合い活かされ活かしあうこと。 今私達の社会で多く耳にする言葉として、「循環型社会の構築」と言うように「循環」と言う言葉がキーワードになっています。ただ本来の地球上で行われている自然循環と言うものと、少し異なっているところがあるように思われます。 地球レベルでの循環は輪廻転生だと思います。ひとつの物体としてこの世に生まれ、その役目を十二分に果たしてやがては命の終わりを向かえひとつの物体としての終末を迎えたと同時に、形を変えて他の圏に出で、立場や役割を変え新しい命へとわが身を移していくことだと思います。衣・食・住それそれぞれにおいて、循環できるものつくりが成されていない今も続いています。廃棄物とならないものつくり、廃棄物になるまでの時間を多く作り出すことが出来るものつくり、再利用する設備があるから、何を造ってもかまわないのではないと思います。再利用施設が作動しなくてもいい物つくりでなければ本来の循環とはいえないということです。 時代の変化経済の変化からこれまで見えてこなかったことが見えるようになり、京都をはじめ全国で暮らし環境へ目を向ける人たちが増えてきた現実があります。 例えば、これまで河川の都市部における状況は、コンクリートで囲まれた排水路的なものばかりでした、そこに生き物は生きる場を失い生活できない状態であるために存在していなかったと言えます。また雨水の貯水に関しても、公共建築物などを利用した貯水施設が作られ始められたり、浸透性の道路舗装を始めたりと工夫されるようになりその他にも交通機関そのものが時代変化をし始め、自転車タクシーや100円バスなどに加えて、当然車の排出ガスの削減を目指すことにも力が注がれています。 いわいる環境都市を目指すには本来の自然界の流れ、気候の変化、それに応じる外界の変化、その度ごとに変わる主役たちがその季節を体全体で表現し、その表現されたものを私達人間も含めて楽しむことが出来る空間とする必要があります。 それは単なる理想郷ではありません、現実に私達が住む場所なのです。緑があれば、虫もつく、ついた虫を殺虫剤で殺すことより、虫がつきにくい植栽などのの混植で防ぐ工夫、水の汚れは、自然の治癒力で浄化できるようなくらいにまで使用し排出することが必要です。京都の町全体がビオトープであることを認識しその生態系を守ることがこれからの街づくりの基本となるべきものです。 |